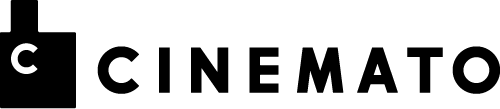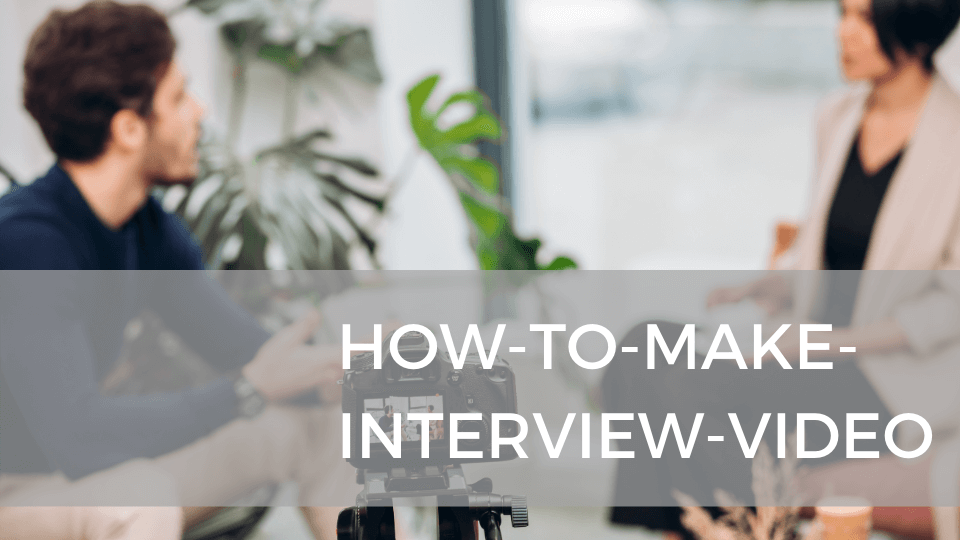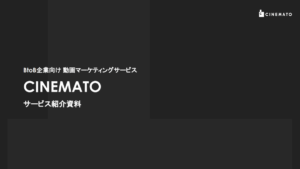「インタビュー動画の作り方が知りたい。」
お客様の声や、社員紹介など、様々なシーンで活躍するインタビュー動画。
中でも商談などで使用するお客様インタビュー動画が人気急上昇中です。
競合と比較される中、ユーザーの信頼を獲得し、受注率を高める効果があります。
インタビュー動画の作り方を知り、ぜひ活用していきましょう。
そこでこの記事では、インタビュー動画の作り方に関する下記の内容をご紹介いたします。
- 撮影に必要な機材
- インタビュー動画撮影のコツ
- 編集のコツ
他の動画と比較すると初心者でも制作しやすいため、ぜひ挑戦してみてくださいね。
それでは、初めにインタビュー動画を撮影するために必要な機材を確認していきましょう。
目次
インタビュー動画の撮影に必要な機材

初めに、インタビュー動画を撮影する際に必要な機材を確認していきましょう。
- カメラ(2台以上)
- 照明
- マイク(特にピンマイク)
- 三脚(可能であればジンバル)
- 動画編集ソフト
インタビュー動画を制作するにあたっては、上記のような機材が必要です
カメラ(2台以上)
インタビュー動画を撮影するなら、2台以上カメラを用意するのがおすすめです。
映像に動きをつけるため、2台同時に利用しインタビューカットとインサートカットの両方を撮影するようにしましょう。
もし、2台以上用意するのが難しい場合は、広角単焦点レンズがおすすめです。
1つのレンズで撮影しますが、編集時に遠近2台のカメラを利用したように見せることができます。
照明
インタビューイーをよりきれいに映すために、照明を利用しましょう。Youtuberなども顔色がよく見えるように、照明を利用して撮影しています。
照明を利用することで表情が明るく見えるので、インタビュー動画を制作するなら照明を用意するのがおすすめです。
マイク
インタビュー動画の撮影に必須とも言えるのがマイクです。
カメラに内蔵されたマイクでは音声が小さくしかはいらなかったり、音声がこもったりしてしまうことがあります。
そこで、音声録音専用のマイクを使用しましょう。インタビュー動画においてメインコンテンツとなる音声は、非常に重要な要素となります。
できれば動きやすく、目立たないピンマイクがおすすめです。
三脚(ジンバル)
インタビュー動画を撮影する際、映像がブレないよう三脚を利用します。
もし、ドキュメンタリー形式の動画を撮影するのであれば、ジンバルという手ブレを補正する道具を準備しましょう。
映像がぶれて撮影し直しとならないように、必ず用意しましょう。
動画編集ソフト
撮影が終わったら、動画編集が必要です。有料の動画編集ソフトがおすすめですが、初心者の方であれば無料のソフトでも大丈夫でしょう。
必要であれば、こちらで無料、有料の動画編集ソフトを紹介したページを用意しております。
以上、インタビュー動画の撮影に使用する機材をご紹介しました。インタビュー動画の撮影は、他の実写映像よりも、少ない機材で対応可能です。
機材が揃ったら、次はどんな映像を撮影したらよいのか。
インタビュー動画の基本的な構成を確認していきましょう。
【効果がでやすい】おすすめの動画構成
ここでは、インタビュー動画の基本的な構成を確認していきましょう。
今回は、商品・サービスに関するインタビュー動画の基本的な構成をご紹介します。
まず、全体の流れとしては下記の通りです。
基本構成
インタビュー動画の基本的な構成は、次の通りです。
- 事業や会社の紹介
- 課題の共有
- 導入のきっかけ(導入理由)
- 実際に使ってみた感想
- これからやっていきたいこと
事業や会社の紹介
初めに、どんな事業をやっているのか、どんな会社であるかを紹介します。ここでは、簡単に会社名や事業内容に触れる程度で問題ありません。
もし、有名企業がおすすめしているとなれば説得力が増します。
大手企業にサービスを導入していただけたら、ぜひインタビュー撮影を交渉してみましょう。
課題の共有
次に、企業が抱える経営上の課題を共有します。
動画を見せる相手は、同じような悩みを持つ企業がターゲットになります。課題を共有することで、自分ごと化してインタビュー動画を見て頂くことができるのです。
導入のきっかけ(導入理由)
なぜそのサービスを選んだのか、導入のきっかけを共有します。
例.
~の機能が魅力的だったから。など
サービスの訴求ポイントなどと同じであれば、より効果があります。
実際に使ってみた感想
サービスを使った上で、どんなメリットがあったのかを紹介します。
課題がどのように解決できたか、どんな対応してもらえたかを伝えるとより効果的です。
ユーザーが気になるのは、使う前と使ったあとのギャップ。そのギャップに不安を感じています。
そこでインタビュー動画を使った良い口コミがあれば、サービスを導入するにあたっての不安を軽減できるのです。
これからやっていきたいこと
インタビューを受ける側が、今後展開したい事業展望について話します。
サービスを導入したことで、その未来へ一歩近づけたということが重要になります。
以上が基本的なインタビュー動画の構成になります。
課題に対し、どんなサービスを使って、どんな効果があるのか。
第3者が語ることに意味があります。また実在する企業がその効果を語ることに意味がるのです。
では、実際にインタビュー動画の事例を見てみましょう。
インタビュー動画の制作事例
ここでは、過去にCINEMATOが制作したインタビュー動画の事例をご紹介します。インタビュー動画を制作する際にぜひ参考にしていただければ幸いです。
freee株式会社様
エンタープライズでも「クラウド会計ソフトと言えばfreee」という純粋想起の市場構築のため、個人事業主ではなく、企業向けに制作したインタビュー動画です。
視聴者に注目してほしい機能はグラフィックで可視化することで、プロダクト利用のメリットのイメージがつきやすいようにしています。
株式会社Game With様
株式会社Game Withは、ゲーム情報等のメディア事業を展開する会社です。
採用活動において実態とは異なるイメージを持たれがちという課題に対して、会社のカルチャーや働いている人を中心に紹介する採用動画を制作しました。
カルチャーやブランドなど、目に見えないイメージを伝える場合において、インタビュー動画はとても相性がいい動画の手法の1つです。
インタビュー中の映像にインサートカットを挿入することによって、話している内容をより具体化的にイメージしやすくなるような工夫を施しています。
株式会社ENERGIZE様
セムコ社が提唱するセムコスタイル経営を、コンサルティングパッケージにまとめたCMP(チェンジメーカープログラム)の紹介動画で、サービスの紹介促進や、LP内でのCVR向上を目的とした動画導入事例です。
冒頭で経営者のインサイトをつくインタビューを入れ、一気に視聴者の興味関心を惹く構成にしています。また、「社員の主体性を軸に事業を発展させたい」というニーズの裏にある、本当に社員が変わっていくか不安という視聴者の悩みや課題感を解消できるように気をつけながら、動画を制作しています。
株式会社EXIDEA
CINEMATOの運営母体である株式会社EXIDEAの会社紹介動画・採用動画です。
会社のコアなバリュー「THE SHARE」や「1メディア1経営」というキーワードをテーマとして、会社が日々大切にしている考え方や社風をインタビュー形式で紹介している採用動画の事例です。
インタビューの合間に見える笑顔や笑い声によって、和やかな社内の雰囲気が伺えるようにも工夫しており、就職希望者の不安払拭を狙っています。
以上、インタビュー動画の事例をご紹介いたしました。どんな動画を制作していきたいのか、イメージを膨らませていくうえでの参考になれば幸いです。
続いては、このような動画を制作するコツを確認していきましょう。
インタビュー動画作り方のコツ【撮影・編集】
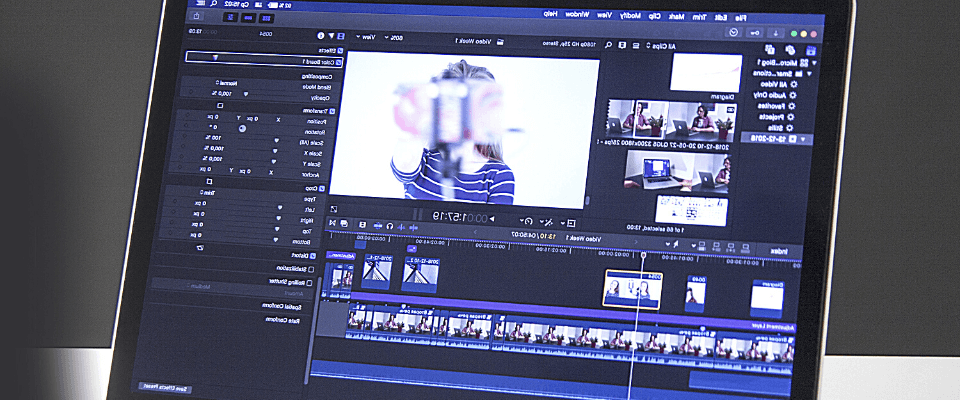
インタビュー動画の基本的な構成がわかったところで、撮影や、編集する際のコツをご紹介いたします。
コツを利用することが、効果的なインタビュー動画の第一歩に繋がります。
撮影のコツ
複数アングルで撮影
複数のアングルで撮影することで、一回のインタビューで変化を持たせた映像制作が可能です。
複数アングル撮影、もしくは広角単焦点レンズを利用して撮影しましょう。
仮に、1つのアングルだけで撮影すると、変化がなく面白みのない映像となります。
ユーザーが閲覧途中で離脱してしまう可能性が高まるので、注意が必要です。
カンペを利用しない
インタビューをする際は、セリフを決めて短時間で話してもらうのではなく、インタビュー時間を長く取りましょう。
自然な印象にするには、その中で使用できるカットを選ぶことがポイントです。
ただし、何も決めていないと何が伝えたいのかわからなくなってしまいます。
インタビュアーとインタビュイーの間で事前に質問のすり合わせは必須です。
ブレの少ない映像
ジンバル(手ブレが少なくなる装置)や三脚を利用して、ブレの少ない映像を撮影しましょう。
映像がぶれると、使い物になりません。撮影し直しとならないよう、ジンバルもしくは、三脚の利用することがポイントです。
以上、撮影のコツを紹介しました。続いては、撮影した映像を編集するコツを紹介いたします。
編集のコツ
インサートカットの活用
インサートカットとは、映像の中に他の映像やイラストなどを挿入して補足する編集方法です。
インタビュー内容だけではわかりにくい内容を説明・補足するために利用します。
例えば、サービス導入の結果どんな効果があったかというのは、口頭で話すだけではイメージが伝わりにくいものです。
グラフを利用することでより効果を伝えやすくなります。
テロップを入れ、内容を補足する
登場人物やサービス名、その他補足したい内容をテロップに入れ視覚、聴覚両方でユーザーに情報を届けます。
映像にメリハリが出るほか、視聴者の記憶に残るインタビュー動画とすることができます。
尺は3分以内に収める
サービス紹介用のインタビュー動画を制作するなら、3分以内に収めましょう。伝えたいこと以外の情報を削ぎ落として編集するのがコツです。
長時間に動画になってしまうと、何が伝えたかったのか、わかりにくくなってしまいます。
伝えたいメッセージを絞り、内容を凝縮することが重要です。以上、インタビュー動画の作り方のコツを紹介いたしました。
作り方がよくわからない時は、CINEMATOにご相談を
インタビュー動画の作り方のコツはいかがだったでしょうか?
インタビュー動画を活用すれば、お客様の不安を軽減することが可能です。
導入したら「どんなメリットがあるのだろう?」「ちゃんと効果がでるのかな」という購入前の不安な気持ちを解消できます。結果的に、その不安の解消が受注率の向上に繋がってくるのです。
こちらの作り方を参考にして、ぜひインタビュー動画を活用してみてくださいね。
また企業がインタビュー動画を活用するなら、ある程度のクオリティが求められるのも事実。
初心者であれば撮影や編集方法に不慣れなのは当然で、クオリティが心配かもしれません。
もし、初めてインタビュー動画を検討中であれば、ぜひCINEMATOまでご相談ください。
CINEMATOでは、サービスの魅力を最大限に引き出すインタビュー動画を制作可能です。
コンサルティング会社出身のプランナーが、インタビュー動画で伝えたい訴求ポイントをうまく引き出します。
CINEMATOのインタビュー動画の制作実績や料金を知りたい方は下記のボタンより御覧ください。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。

新卒でデロイト・トーマツグループに入社。その後、株式会社プルークスを共同創業、取締役に就任。大手、メガベンチャー企業を中心に多数のwebマーケティング・プロデュースを手がける。
2017 youtube ads leaderboard下期受賞経験を持つ他、2018年アドテック関西へスピーカー登壇。