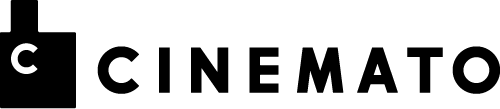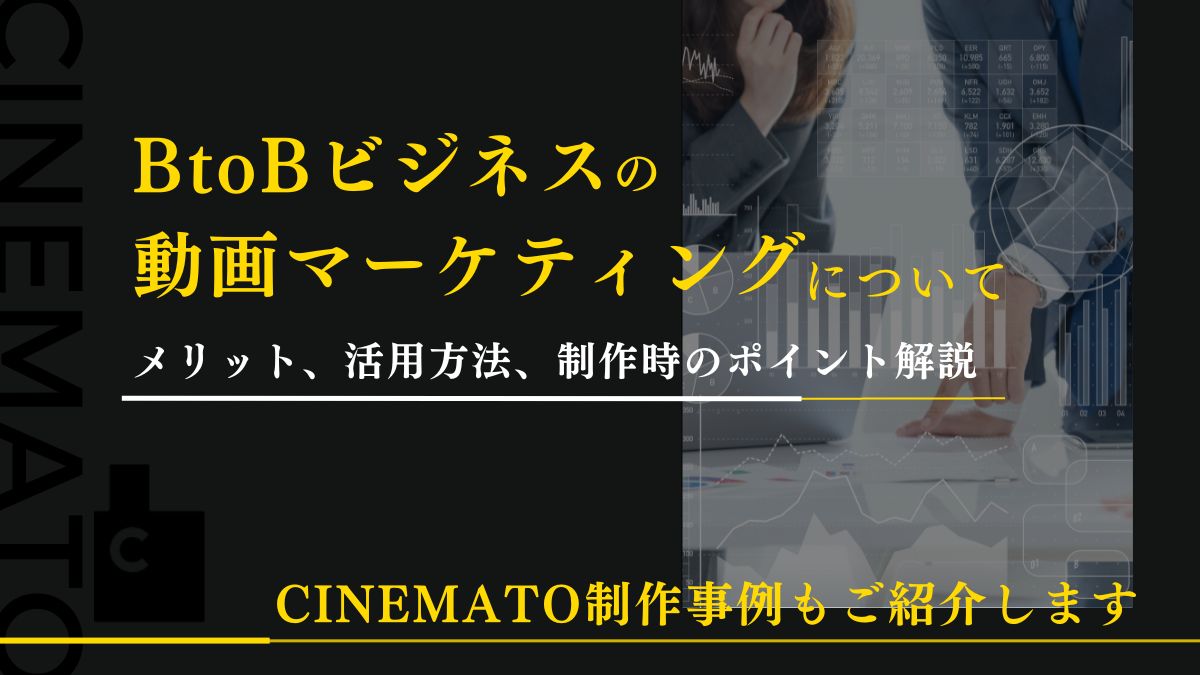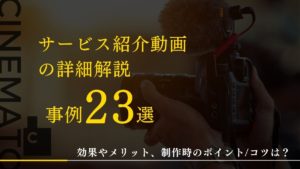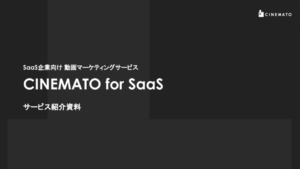近年様々なビジネスの現場でデジタル技術の導入が進められ、なかでも動画マーケティングには一際大きな注目が集まっています。
もちろん、BtoBビジネスを運営する企業も、その例外ではありません。
しかし、初めて動画制作に取り組む企業にとっては「BtoBの現場で動画を活用する方法は?」「BtoBビジネスの動画制作の方法は?」と、不明点も多いことでしょう。
そこで、本記事では、BtoB企業が動画マーケティングを実践するメリットや有効な活用方法、実際に動画制作をおこなう方法について解説します。
- 動画コンテンツの特徴
- BtoB企業が動画を活用するメリット・デメリット
- 動画コンテンツの活用シーン
- BtoB企業の動画制作事例
こちらの記事が多くの企業にとって、動画マーケティングを開始するきっかけとなれば幸いです。それでは、順番に内容を見ていきましょう。
BtoB動画マーケティングを活用したリード獲得に興味のある方は、以下の「リード獲得に繋がる動画マーケティング戦略」の資料も参考になるかと思います。
当記事で紹介しているBtoB動画マーケティングの情報だけでなく、社内での映像制作検討時にぜひ、以下の資料もあわせてご活用ください!
\無料ダウンロードはこちら/
目次
BtoBビジネスで動画マーケティングが注目される背景

ここではまず、BtoBビジネスで動画マーケティングが注目される背景を説明します。
多くの企業が動画を含むデジタルマーケティングを推進する背景には、スマートフォンの普及やデジタル技術の発達といったプラスの要因、新型コロナウィルスの蔓延を発端としたマイナスの要因が挙げられます。
時代の流れとそれに伴う行動様式の変化を理解し、デジタルマーケティングの効果を最大限発揮しましょう。
拡大する動画市場
スマートフォンの普及や通信技術の発達、さらに新型コロナウィルスによるライフスタイルの変化により、現在動画市場は急速な成長を続けています。
2021年におこなわれた一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)の調べによると、2022年動画配信市場規模は推計4530億円(前年比107%)。国内の動画市場規模は2023年以降も成長を続け、2027年には5670億円に達する見込みです。※1
※1. 出典:一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)『動画配信市場調査レポート2023』
おうち時間が増えたことで動画視聴時間が増加
次に、一般の動画視聴者となるユーザーの行動の変化を見てみましょう。
スマートフォン利用者を対象に、コロナ禍により在宅時間が増えたことで、どのような活動に時間が増えたかを聞いたところ、最も多かったのは「無料動画を見る(27.5%)」となっています。
「テレビ番組を見る(26.3%)」を上回ってネットでの動画視聴が伸長した点から、多くの企業や動画配信者から注目される結果となっています。※2
※2. 出典:株式会社インプレス(インプレス総合研究所)『動画配信ビジネス調査報告書2020』
営業機会損失によるオンライン化の加速
また、新型コロナウィルスの影響で行動様式の変化を強いられたのは個人だけではありません。
多くの企業は非対面・非接触での事業活動や、コロナ禍に適したマーケティングを推進するようになりました。
なかでも、多くの企業が取り組んだのは「商談・会議のオンライン化」です。非対面での営業活動のツールとして有効な動画コンテンツは、現在では多くの企業によって採用されています。※3
※3. 出典:ITR Market View:SFA/統合型マーケティング支援市場2022
企業のデジタルマーケティングにおける動画活用の重要性が増加
こうした環境下で、企業のデジタルマーケティング施策において動画活用の重要性が高まっていると考える企業は多く、その割合は実に85%にも上ることがわかりました。※4
※4. 出典:アライドアーキテクツ「企業のデジタルマーケティング施策における動画活用の実態調査 2021」
業務中に動画を見た経験のある層は、動画施策に前向き
実際に、コロナを機に動画の活用を始めた企業は多く、その用途は営業目的のものに加え、社内教育をはじめとした社内向けのものも多くなっています。
種類を問わず動画は概ねポジティブに受け取られ、業務中にこうした動画を見た経験のある層の内86.9%は「コロナ後もこうした取り組みを続けてほしい」と考えているようです。※5
※5. 出典:J stream『コロナ環境下における動画活用に関する調査』
Webを活用した購買決定をおこなう企業が増えている
動画マーケティングを含むデジタル施策が非常に身近になった今、企業の取引先選定方法にも変化が生じています。
インターネット上で質の高い多くの情報を仕入れることができるようになった現在では、BtoBを含む多くの取引時、その情報収集にインターネットが活用されています。
つまり、積極的にインターネットを利用した情報発信をしていくことは、今後の企業の成長に直結するとも言えるでしょう。自社の事業を効率的かつ着実に成長させていく上で、今や動画の活用は欠かせません。
動画コンテンツの特徴
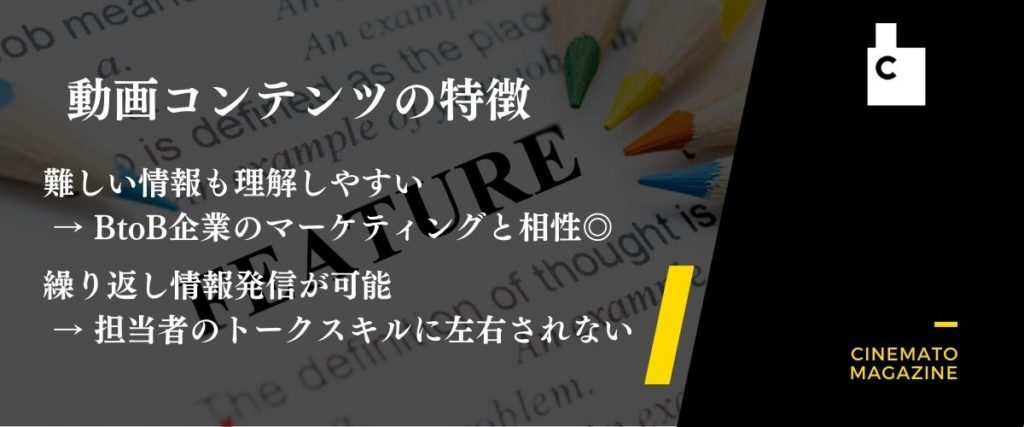
動画には文章や静止画と比べ、短い時間で正確に情報を伝えられるというメリットがあります。
一般の消費者をターゲットとするBtoCビジネスでも企業をターゲットとするBtoBビジネスでも、情報を受け取りその後の判断をおこなうのが人間であることに違いはありません。
ここでは、動画そのものが持つ特徴を、整理しましょう。
BtoB企業のマーケティングと動画は相性がよい
BtoBビジネスにおける製品や事業内容は、BtoCビジネスのそれと比べて理解が難しいというのが特徴です。そのため、テキストやスライドを使って説明を行う際には、膨大な資料が必要となります。
時には、「資料がわかりにくい」「最後まで読む時間がない」といった理由で見込み顧客を逃してしまう可能性もあるでしょう。
一方、動画を用いて自社の事業や製品を紹介した際には、映像(実写・アニメーション)と言語(会話・ナレーション・テロップ)を用いて、短時間で多くの情報を伝達することが可能です。
そのため、動画には情報の受け手が感じるストレスも非常に小さく抑えられるというメリットもあります。
顧客にとって理解の難しい内容であればある程、動画は大きな効果を発揮します。これがBtoBビジネスと動画は相性が良いと言える理由です。
担当者のトークスキルに左右されない情報発信が可能
このように、BtoB営業の場面で多く利用される動画資料には、他にも特徴があります。それは「毎回一定の水準で繰り返し商品・事業説明をおこなえる」という点です。
BtoB営業の現場では、動画は雄弁な営業マンとして商品や事業の説明をおこないます。新人からベテランまで、担当者のトークスキルに左右されず顧客に情報提供できる点は、動画活用時に得られるメリットです。
「BtoBマーケティング」と「BtoCマーケティング」の違い

ここでは「BtoBマーケティング」と「BtoCマーケティング」の違いを、顧客の性質や購買決定までのプロセスといったところに焦点を当てて見ていきます。顧客の性質を正しく理解し、効果的な訴求に役立てましょう。
ターゲットの違い
まず、BtoBビジネスとBtoCビジネスでは、対象のターゲットが異なります。BtoB(Business toBusiness)のターゲットは企業や団体、BtoC(Business to Customer)のターゲットは個人です。
個人を対象にビジネスを展開する場合は、対象の顧客にその製品を気に入ってもらえるかという点に焦点を当てますが、BtoBビジネスの場合、それほど単純ではありません。
重視されるポイントの違い
BtoB商材の購入時、顧客は製品やサービスの購入によって「どのような課題が解決できるか」「どれだけの費用対効果を得られるか」といった点に注目します。
一方、BtoCの購買では「自分にとって良いものか」という個人的趣向が重視されることがほとんどです。お気に入りのブランドや期間限定特典に対する購買ハードルは自ずと低くなるでしょう。
検討期間の長さの違い
BtoCとBtoBでは、導入決定プロセスの違いから、検討期間の長さに違いが生じます。
BtoCのターゲットとなる顧客の場合、基本的に購入決定までのプロセスは個人で完結します。そのため、衝動買いの場合には認知から購入決定までのプロセスが、ものの数分というケースも珍しくありません。
一方、BtoBビジネスの顧客は企業や団体です。組織や購入物品による違いはありますが、多くの場合稟議書の通過といった工程を踏む必要があり、購買や契約の決定までに数ヶ月を要する場合もあるでしょう。
このように、BtoC・BtoBでは対象となる顧客の属性の違いから、購入時に重視されるポイントや購入決定までのプロセス・期間に違いが生まれます。顧客の購買行動の特徴を理解し、適切な訴求をおこないましょう。
企業のPRに動画を活用するメリット
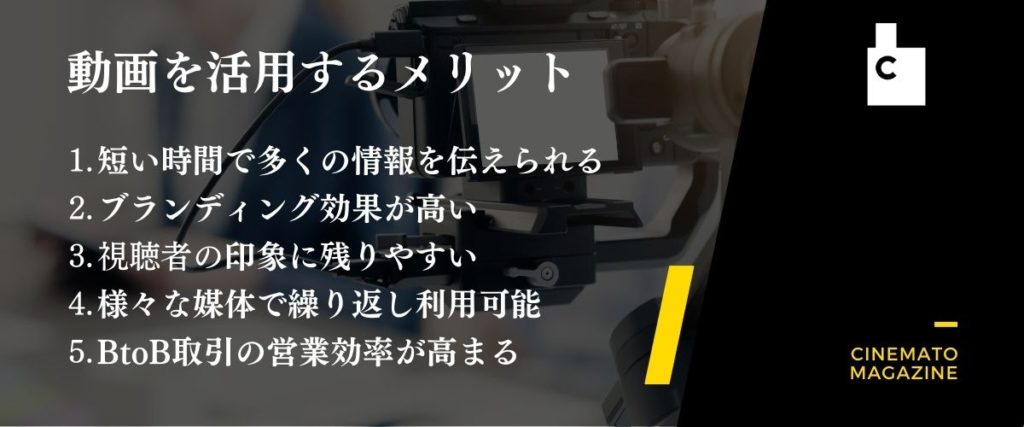
ここまでご紹介してきたBtoBマーケティングの特徴を踏まえ、ここからはBtoBビジネスに取り組む企業が動画を活用するメリットについて、具体的に解説します。
ここで紹介する内容を整理し、動画マーケティングを活用することで得られるメリットを最大限に活かすことのできる動画制作をおこないましょう。
BtoBにおける動画活用のメリットは以下の5点です。
動画を活用するメリットは?
- 短い時間で多くの情報を伝えられる
- ブランディング効果が高く記憶に残りやすい
- ライバル企業に先駆けて取り入れることで印象に残りやすい
- 様々な媒体で繰り返し利用しやすい
- BtoB取引の営業効率が高まる
文章や静止画と比較して、短い時間で多くの情報を伝えられる
まず、文章や静止画と比較して短時間で多くの情報を伝達できる点がBtoBビジネスで動画を活用するメリットです。
最新の研究によると、1分間の動画で伝達できる情報量は文字媒体に置き換えると英単語180万語に相当すると言われています。
また、動画の情報の受け取りには「読む」という行動を必要とせず、動画の内容に興味のない視聴者が「眺める」だけで情報伝達が可能です。
ニーズの顕在化していない層にも無理なく情報を伝達できる動画は、幅広い層へのアプローチに適しています。
ブランディング効果が高く記憶に残りやすい
動画には文字や画像のみでの情報伝達と比較し、記憶に残りやすいという特徴があります。
1971年にアメリカの心理学者によって提唱された「メラビアンの法則」によると、人が受ける印象は「言語情報(7%)」「視覚情報(55%)」「聴覚情報(38%)」によって形作られるとされています。
言葉・映像・音声を組み合わせて構成される動画という情報伝達手段は、文字や画像のみのものに比べて記憶に残りやすく、高いブランディング効果が期待できるでしょう。
ライバル企業に先駆けて取り入れることで印象に残りやすい
このように、情報伝達に動画を用いることで、文字や静止画のみで商品を訴求した際と比べて、大きな効果が期待できます。
つまり、同じ業界の競合の中で自社だけが動画を活用する事で、情報伝達における優位性を持つことに繋がります。
他社以上に顧客の印象に残る取り組みをおこなう事で、問い合わせ件数アップを目指しましょう。
様々な媒体で繰り返し利用しやすい
動画コンテンツは一度制作してしまえば、様々な媒体で繰り返し利用できるのもメリットです。BtoB企業が動画を利用できる場面には、主に以下のようなシーンが挙げられます。
- 自社サイト・サービスページ
- SNS
- Youtube
- Web広告
- 営業ツール
- 社内資料
ご覧いただくとわかる通り、動画は非常に多くの場面で活用することができます。なかでも、SNSやYoutubeといったWebサービスへの動画配信は、多くの人の目に触れることができるでしょう。
動画コンテンツは制作時にある程度の費用が必要ですが、一度制作すればその後は繰り返し再生が可能です。視聴される回数を増やすことで、動画制作の費用対効果を高めましょう。
BtoB取引の営業効率が高まる
動画を活用することで、BtoBビジネスの営業効率が高まる点も見逃せません。営業ツールとして動画を利用することで、具体的には以下のようなメリットが得られます。
動画を利用するメリット
- 短い時間で多くの情報を伝えられる
- オンラインの商談や映像データ送付のみも可能
- 営業担当のスキルに頼らず、一定の水準で説明をおこなえる
- 実物を見せることのできないものの説明が可能
このように、動画の活用は営業の質と量の両方にとって良い影響を与えます。特に顧客にイメージしづらい製品・サービスを販売するBtoB事業者にとって、得られる効果は大きいでしょう。
企業のPRに動画を活用するデメリット
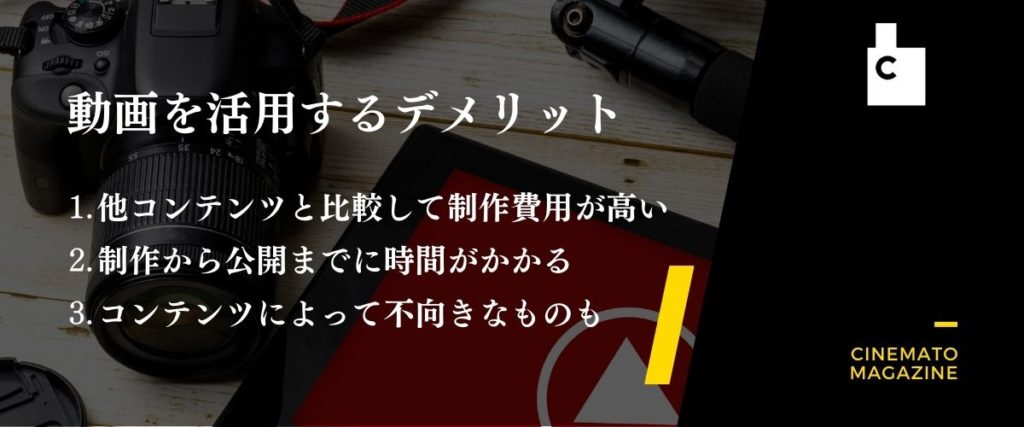
上の章で解説したように、BtoB企業の動画活用からは多くのメリットが得られます。ただ、そこには少なからずデメリットがあるのも事実です。
動画を活用するデメリット
- テキストコンテンツと比較して制作費用が高い
- 制作から公開までに時間がかかる
- コンテンツによって不向きなものもある
ここでは以上のデメリットについて解説します。事前にこれらのデメリットを理解し、動画制作の実施をご検討ください。それでは1つずつ見ていきましょう。
テキストコンテンツと比較して制作費用が高い
企業が動画を活用する際の1つ目のデメリットは、テキストコンテンツと比較して制作費用が高くなるという点です。
動画は企画・撮影・編集の工程から制作され、それぞれに専門的な知識やスキルが必要となります。動画の活用によってどの程度の効果を得られるかを計算し、期待する効果に見合った費用で動画制作をおこなうことが重要です。
制作から公開までに時間がかかる
BtoB企業が動画を活用するデメリットの2つ目に、制作から公開までに時間がかかるという点が挙げられます。
前述の通り、動画制作には多くの工数が必要です。またそこでは専門技術を持った多くの人が関わります。
制作手順に沿って多くの技術者をアサインする必要がある動画制作は、制作期日までを逆算して作業に取り掛かる必要があると言えるでしょう。
コンテンツによって不向きなものもある
企業が動画を活用する際、コンテンツによっては動画が不向きなものがあるという点には注意が必要です。具体的には、教科書のように何度も見返す内容のものがそれにあたります。
教科書のようなコンテンツは、テキストの場合は該当の箇所をブックマークしたり、スクリーンショットを撮影して必要な時に何度も見返すことができます。
しかし、これが動画の場合はどうでしょう?「動画内◯分◯秒」と記録を残し、その都度そこまで動画を進めなければなりません。
ユーザーの利便性を考え、最適な形でコンテンツを配信することを心がけましょう。
動画コンテンツの具体的な活用シーン5つ
ここからは制作した動画コンテンツを実際に使用する、活用シーンを紹介します。現在はスマートフォン利用による動画試聴時間の増加、また通信の高速化といったことを背景に、非常に多くの場面で動画コンテンツを配信できます。
具体的な動画の活用シーンは?
- 会社HP・サービスページ
- SNS
- ウェビナー
- タクシー広告・デジタルサイネージ
- 商談時の営業ツール
動画を活用する目的や、得たい効果は何かといったことをもとに、動画の活用場面を検討しましょう。
Web上のサービスページに動画を埋め込む
BtoB動画コンテンツを配信する場面の1つ目は、会社ホームページやサービスページです。
自社サイトに動画を掲載する際は、外部サイト掲載時と異なり、動画の尺やサイトデザインそのものを自由にカスタマイズできるというメリットがあります。
もちろん掲載するコンテンツの目的やターゲットは自由です。動画コンテンツそのものだけでなく、それを配置するサイトのデザインにも工夫を凝らし、多くのユーザーに訴求することを心がけましょう。
また、自社保有サイトにはすでに自社や製品に興味を持っているユーザーが多く訪れます。商品の宣伝だけでなく自社のファンや既存顧客に喜ばれるコンテンツを配信することも、再生数を伸ばすために必要なポイントです。
SNS広告のクリエイティブに動画を利用する
現在様々なSNS媒体で広告を配信する企業が増えており、もちろんBtoB企業もその例外ではありません。
SNS広告はユーザーの登録情報をもとに配信先を選定するため、ターゲティング精度が高いのが特徴です。
各SNS媒体のメインユーザーの属性や、広告配信フォーマットを知ることで、費用対効果の高い広告配信をおこないましょう。
ウェビナーを配信してリード獲得に繋げる
製品や事業の理解に専門知識を要し、購入単価の高いBtoB商材を販売する際、「認知」から「購入」の間に「顧客教育」という過程を踏むことも少なくないでしょう。
顧客教育とは製品に興味・関心を持ったユーザーの製品理解を促し、購買動機を強めるためにおこなうマーケティング施策です。
ウェビナーを通して認知客に資料請求やメルマガ登録といった購入前行動を促すためにも、BtoB動画は活用されています。
タクシー広告・デジタルサイネージで配信するWeb CM
タクシー広告や繁華街・電車内のデジタルサイネージも、BtoB動画の代表的な配信場所の1つです。
特に、タクシーは企業の経営者層や富裕層といった、会社の決裁権を持つ人物が利用する交通機関です。
プライベート空間で眼前50センチで配信されるタクシー動画は、日々多忙なスケジュールをこなすターゲットにも広告を視聴してもらえる可能性があるという、他の媒体に無い特徴があります。
商談時の営業ツールとして利用する
取引先との商談時は、BtoB動画の代表的な活用場面です。商品や事業の内容が複雑でわかりにくいBtoB商材の営業において、短時間でわかりやすく説明をおこなう動画コンテンツは、心強い味方となります。
また、動画を活用することで営業担当者のトークスキルに頼らず常に同じレベルで商品説明をすることができるため、業績の安定や教育費の削減といった効果も期待できます。
BtoBマーケティングで人気がある動画の種類
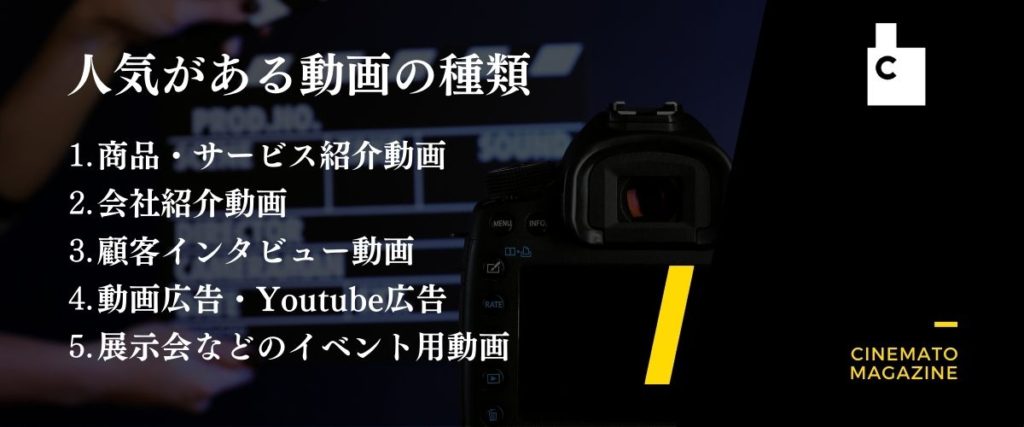
このように多くの場面で利用されるBtoB動画には、主にどういった種類があるのでしょうか?ここではBtoB動画を大きく5つの種類に分けて説明します。
自社ではどういった動画制作が必要なのかをイメージしながら、1つずつ見ていきましょう。
活用される動画の種類
- 商品・サービスの紹介動画
- 会社紹介動画
- 顧客インタビュー動画
- 動画広告・Youtube広告
- 展示会などのイベント用動画
商品・サービスの紹介動画
商品・サービスの紹介動画は、販売する商品の概要や詳細の説明、発売時のイメージ訴求といった幅広い内容で制作されるBtoB動画です。
動画の目的にも「認知拡大」「購入促進」「ブランディング」「アフターフォロー」と幅広く、商品の認知フェーズやマーケティング戦略に応じて使い分けることができます。
商材の有形・無形に合わせて実写・アニメーションを使い分けることも有効です。
会社紹介動画
会社紹介動画はBtoBビジネスをおこなう企業の、歴史や事業内容といった情報を顧客に知ってもらうために制作します。
BtoBの取引先を選ぶ際、取引先企業のこだわりや、実績、また相手企業は信頼できる企業なのかといった、製品以外の部分で判断することも少なくないでしょう。
会社紹介動画には「認知拡大」と「ブランディング」効果が期待できます。視聴者が共感できるシナリオやキーワードを組み込み、顧客と心理的な繋がりを築いていきましょう。
顧客インタビュー動画
顧客インタビュー動画は既存顧客協力のもと、商品や企業に対して感じたことを話してもらう動画です。
BtoBの商品はBtoCのそれとは違い、一般のクチコミ情報を得にくいという特徴があります。
また、一度の取引金額も比較的大きくなることが多いため、購入側の企業としては少しでも多くの情報を集めてから取引に進みたいと考えるでしょう。
BtoB企業は顧客インタビュー動画を配信することにより、見込み顧客からの信頼を得られると同時に、既存顧客からの新たな気づきを得られる可能性もあります。
事前にアンケートを実施し「ぜひ話を聞いてみたい」と感じる取引先があった場合には、動画制作を前向きに検討しましょう。
動画広告・Youtube広告
動画広告・Youtube広告の配信をおこなう場合は、他の目的で制作した動画を使い回さず、広告専用の動画を制作するのがおすすめです。
というのも、動画広告配信時には、動画の尺や動画アスペクト比(縦横比)といった、媒体独自のルールが存在します。
また、例えばYoutube広告であれば、「再生開始から5秒後にスキップ可能」といった特徴に合わせて動画の構成を組む必要があります。
動画広告は現在企業が最も注目するPR施策の1つであることに間違いありません。ただし、配信にはそれなりのコストがかかります。
配信予定の媒体の特徴を抑え、効果を最大化できる動画コンテンツを制作しましょう。
展示会などのイベント用動画
展示会をはじめとした出展イベントは、BtoBの新規取引先を開拓するための重要な場面です。こうした場面においても、積極的に動画を活用する企業が増えています。
展示会で使用する動画の内容は会社紹介から製品紹介まで幅広く、来場者の属性や自社の認知度に合わせて使い分ける必要があります。
具体的には、自社の認知度が低い場合には会社紹介動画を用いて、企業の認知拡大を目的に。知名度がある企業は新製品の魅力や特徴を伝える商品紹介動画を使用すると良いでしょう。
いずれにしても、来場者の足を止め、「少し見てみようか」と思わせる、興味を惹く仕掛けが不可欠です。
【解説】CINEMATOの最新BtoB動画制作実績10選
事例1. 荏原製作所株式会社様
| 動画の種類 | コンセプト動画 |
|---|---|
| ポイント | 半導体装置という製品イメージがつきにくい課題がある商材に対して、その製品や技術が生活のインフラを支えているということが伝わりやすい動画を提案しました。半導体が実現する世界を“モンゴルでもスマホが普及した世界“という表現で意外性をもたせる等、技術が生活のインフラを支えていることを日常生活の映像に落とし込んでいる点がポイントです。 |
事例2. 株式会社KAKEAI様
| 動画の種類 | サービス紹介動画・WebCM |
|---|---|
| ポイント | ビジネスでのコミュニケーションにも「本音が必要」という内容をわかりやすく伝えるため、日本の歴史上最も上司と部下で本音のコミュニケーションが足りなかったと言われている織田信長と明智光秀をキービジュアルに採用しました。サービスの新しさ、気軽さを表現するためグリッドデザインを使いスタイリッシュな映像表現にしている点もポイントです。 |
事例3. 株式会社インフキュリオン様
| 動画の種類 | サービス紹介動画 |
|---|---|
| ポイント | 無形サービスやSaaS、新しい技術・サービスが持つ「言葉だけでは理解が難しい」という特徴に対して、アニメーションを用いた分かりやすい表現でアプローチしています。サービスで”出来ること”を紹介した後、導入意欲が高まっている視聴者に向けて、動画後半で「気になっていること・懸念点(導入障壁)」を事前に解説し、動画視聴中のユーザーの態度変容を考慮した構成設計としている点もポイントです。 |
事例4. 株式会社Hubble様
| 動画の種類 | サービス紹介動画 |
|---|---|
| ポイント | 実際のツール画面を動きのあるアニメーションでみせることで、シンプルで使いやすいツールのメリットを分かりやすく訴求しています。 |
事例5. 株式会社カラクリ様
| 動画の種類 | サービス紹介動画・インタビュー動画 |
|---|---|
| ポイント | シンプルなイラストと、滑らかでわかりやすいアニメーションを用いて、サービスの特徴を分かりやすく解説しています。アニメーション動画を利用すれば、SaaSといった無形商材でも、サービスの使い方や、特徴、メリットなどを可視化し、具体的にイメージしやすいサービス紹介とすることが可能です。後半では、実際にKARAKURI assistを利用している企業様の顧客インタビューを取り入れています。顧客インタビューは、サービスの信用度を高める方法としてとても効果が大きい映像表現です。 |
事例6. freee株式会社様(クラウド会計freee)
| 動画の種類 | 動画広告・Youtube広告 |
|---|---|
| ポイント | 会計freee=小規模事業者向けという認知を100-200名規模の企業でも利用できるという認知に変えるため、変化と機能メリットをシナリオと演出に落とし込んで表現しています。 freeeを利用することで営業・情報システム・経理・経営者のかくポジションのワークフローにどのような変化が起きるのか。問題提起と解決後の姿をBefore・After形式でわかりやすく説明しています。 |
事例7. 株式会社リクルート様 カムバック採用サービスAlumy
| 動画の種類 | 商品・サービスの紹介動画 |
|---|---|
| 予算 | 80万前後 |
| ポイント | カムバック採用という新しい概念を伝えるため、カムバック採用が求められる時代背景や企業課題から動画を始め、サービス詳細の説明へと繋げていくシナリオを制作しています。 |
事例8. トランスコスモス株式会社様
| 動画の種類 | 会社紹介動画 |
|---|---|
| 予算 | 100万前後 |
| ポイント | なぜトランスコスモスがBIS事業に取り組むのかという「意義」を伝えることで、学生に一度話を聞いてみたいと思ってもらうことを目指して制作しました。採用における母集団形成を目的とした映像です。 |
事例9. 株式会社ポテパン様(POTEPAN CAMP)
| 動画の種類 | 顧客インタビュー動画 |
|---|---|
| 予算 | 100万前後 |
| ポイント | 「こんな自分でも大丈夫?」とエンジニアになりたいが一歩踏み出せないユーザーをターゲットにしています。スクール利用者の生の声(共感エピソード、一歩踏み出すきっかけ、選んだ理由、今後のキャリアなど)をインタビュー形式で表現することで、こんな自分でも大丈夫なんだと思わせるような構成にしています。 |
事例10. Micoworks株式会社様
| 動画の種類 | 展示会などのイベント用動画 |
|---|---|
| 予算 | 100万前後 |
| ポイント | カット展開を早くしてテンポ感を良くすること、テキストを大きくして視認性を高めることで、展示会の通行人の興味を引いて足を止めてもらうことを目的とした演出になっています。 |
動画制作依頼から納品までの流れ
ここまでの章でBtoB動画の活用方法や、それを公開する場面を見てきたことで、そろそろ動画制作の具体的なイメージが湧いてきたのではないでしょうか?
ここからは「実際にどのような手順を踏んで動画を制作するのか?」という点について解説します。
この章では具体的に以下の内容を説明します。
- 動画制作の目的・予算・納期の設定
- ヒアリング
- 企画構成の提案・見積り
- 撮影・イラスト制作
- 編集
- MA(MultiAudio)
- 納品
それでは順番に見ていきましょう。
動画制作の目的・予算・納期の設定
BtoBの動画制作時にまずおこなうのは、動画の目的・予算・納期の設定です。
目的の設定とは「認知拡大」「ブランディング」「購入促進」「アフターフォロー」といった、動画を配信することによって自社が得たい成果を明確にすることを指します。
ここで予算や納期を設定するのは、動画制作会社とのやりとりをスムーズにするためです。これらの内容を社内でよく話し合い、動画制作の基盤を作りましょう。
ヒアリング
上の項目が決まったら、動画制作会社とコンタクトをとりましょう。
動画制作会社はここでのヒアリングを元に構成やシナリオをはじめとした、全体のディレクションをおこないます。
後から動画の方向性を大きく変更することは困難です。ヒアリング時には聞かれたことに答えるだけでなく、不明点について質問したり、盛り込みたい内容を伝えるなど、「こちらの意図が十分に伝わっている」と感じられるまで、じっくりと話し合いをおこないましょう。
企画構成の提案・見積り
ヒアリング段階で話した内容をもとに動画制作会社が企画構成や見積もりを提示し、問題がなければ契約へと進みます。
この時も追加料金や修正の可否など、気になる点については質問し、疑問をクリアにしておきましょう。
撮影・イラスト制作
事前に作成したシナリオをもとに、実写の場合は撮影、アニメーションの場合はイラストの作成に移ります。
出演する演者や、撮影(イラスト作成)をおこなう技術者のスケジュールによって撮影期間は前後し、短ければ数日、長ければ半年近い時間を要することもあるようです。
撮影にはなるべく同席し、制作側との認識のズレを感じたらその都度修正するようにしましょう。
編集
撮影・イラスト作成を終えたらそれらを編集し、動画を仕上げていきます。
動画の切り貼りによる映像作成、テロップや特殊効果の挿入の2段階に分けてチェックをおこなうのがおすすめです。動画制作会社にこのような対応が可能かどうかも事前に確認しておきましょう。
MA(MultiAudio)
ケースによってはナレーションやセリフを収録スタジオで録音し、音量のバランスを微調整しながら動画に組み込むといった工程が発生します。依頼主の企業もここに同席し、確認しながら調整をおこなうのが通常です。
納品
以上の作業が無事完了し、問題がなければ納品へと進みます。
動画制作時の見積書で確認するポイントとは?
動画制作会社に依頼して動画制作をおこなう際、いくつか注意が必要な項目があります。
後から「そんなことは知らなかった」とならないために、ここでは契約段階で確認必須の項目について解説します。
素材に関する記載があるか
見積書には、費用の発生する項目ごとにその金額が記載されています。
なかでも、見積もり時点で注意して確認する必要があるのは、写真素材や音響で権利費用が発生するものはないか、またそれらがきちんと記載されているかという点です。
素材に関する費用が見積書にない場合、後から追加費用が発生する可能性があります。動画制作をしながら素材を選定していく場合にも、費用の概算は必ず把握するようにしましょう。
著作権の帰属は誰か・使用期間が定められているか
動画の著作権の帰属に関する内容も、見積もり段階で必ず確認するべき項目です。
依頼者の意図に沿って制作された動画であっても、制作物の著作権は制作会社に帰属するのが一般的です。
動画を活用できる場面が限定されないために、二次利用の可否など契約内容の細かな部分まで確認をおこないましょう。
この時トラブルになりやすいのは、映像の使用権に関する問題です。使用期間が限定されたものなのか、半永久的に利用できる動画なのかという点も必ず確認しましょう。
出演者の肖像権をはじめとした権利関係
演者を使って実写動画を制作する際には肖像権も重要な確認項目です。
タレントを起用する際には動画の使用期間や配信場所に関する取り決めがあることもあります。
また、案外注意が必要なのは、自社の社員が出演するケースです。退職後の継続的な動画配信の可否など、万が一に備えて事前に取り決めをおこなう必要があります。
ハイクオリティの動画制作ならBtoBに強いプロの制作会社への依頼がおすすめ
本記事ではBtoB企業の動画マーケティング活用に向けて、動画コンテンツの特徴やそれをBtoB企業が活用するメリット、また実際の動画制作の方法や注意点について解説しました。
近年スマートフォンの普及やコロナ禍でのライフスタイルの変化により、多くの企業が動画マーケティングに注目し、実践を始めています。
ただし、ここには一点注意が必要です。正しい知識やノウハウがないまま動画制作を始めてしまうと、思うような成果が得られないといったことにもなりかねません。
せっかく手間や費用をかけて動画を制作しても、期待する効果を得られなければ何の意味も無く、むしろ動画制作にかけた費用の分だけマイナスです。
そのため、BtoB動画の制作を検討する際には、必ずBtoB動画制作実績の豊富な会社に相談しましょう。
本記事を通して動画マーケティングに興味をお持ち頂き、急速にデジタル化が進むこの時代を事業成長の機会として活かして頂ければ幸いです。
相談無料!
\お気軽にお問い合わせください/

新卒でデロイト・トーマツグループに入社。その後、株式会社プルークスを共同創業、取締役に就任。大手、メガベンチャー企業を中心に多数のwebマーケティング・プロデュースを手がける。
2017 youtube ads leaderboard下期受賞経験を持つ他、2018年アドテック関西へスピーカー登壇。