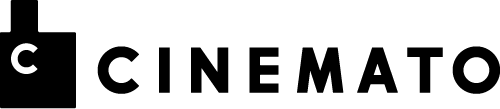How To動画(ハウツー動画)は、スマホの普及により急速に拡がっています。そんなHow To動画は、実はただ使い方を説明するためだけの動画ではありません。
例えば、カメラメーカーが動画編集のHow To動画を出した場合。動画を見てもらえれば、間接的にメーカーの名前や商品を認知してもらうことができます。
How To動画を掲載することが、結果的に商品の購入や認知獲得へとつながることも多々あるのです。
また、How To動画を導入すれば、少なからずサポートセンターの負担を減らすことができます。使い方がわからないというような相談が減れば、その分他の作業に力を入れることができるのです。
このように、How To動画は想像以上にメリットが大きいもの。制作のコツを知って、効果の高いHow To動画を導入しましょう。当ページでは、How To動画が効果的な活用シーンから、動画事例、導入のメリット、動画制作上のコツまでご紹介しております。
まずは、CINEMATOが過去に制作したHow To動画(ハウツー動画)の事例をいくつかご紹介します。
目次
How To動画(ハウツー動画)のCINEMATO制作事例
How To動画制作事例 : 株式会社エフアンドエム様
株式会社エフアンドエム様の提供する労務管理クラウド シェアNo.1アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」のHow To動画です。
トライアル会員のチャーンレート(解約率)改善を目的としたHow To動画であったため、チャーン(解約)が発生している要因である「機能面の説明」を分かりやすく解説しています。
あわせて、トライアルユーザーのインサイトを深掘って「感情的にもオフィスステーションに興味を持ってもらえる」ようなデザインとモーションも意識しています。
初期導入の流れを実際の画面とアニメーション、ナレーションを用いて丁寧に解説している点、エフェクトを使ってユーザーに操作してほしい場所を明確にしている点がポイントです。
「How To動画作り方のコツについて」の章で詳しく解説しますが、How To動画は伝えたいメッセージを1つに絞り、動画の尺を短く、小分けにすることが大切です。
こちらでご紹介しているHow To動画も、初期設定の内容を3つのパートに区切ることで、情報を分かりやすく、また、振り返りやすい尺の長さにしていることがポイントです。
How To動画制作事例 : スターティアラボ株式会社様
スターティアラボ株式会社が提供するAR(拡張現実)を活用して商品や企業のPRをおこなうプロモーションツール「COCOAR(ココアル)」のHow To動画。
ARという新しい技術に対する「操作が難しいのではないか」「特殊な技術が必要なのではないか」という不安を払拭するためのHow To動画です。
ARを想像させる3DCG映像を挟みながらも、操作方法を極力シンプルに表現する演出にすることで、操作方法の簡単さ・ツールへの親しみやすさを訴求しています。
How To動画制作事例 : 株式会社IKUSA様
最後は、少しテイストの違う動画をご紹介します。
株式会社IKUSAの、オンラインでの懇親会・社内レクリエーション、社内研修など、企業のオンラインイベントのために開発されたフードデリバリーサービス「オンラインフードデリバリー」のHow To動画です。
サービスの利用促進を目的とした動画で、サービス紹介動画も兼ねており、「マニュアル動画」という定義に近い動画になっています。
懇談会や社内研修をオンラインで受ける際に「同じご飯を食べられる」という新しいサービスの形であることから、サービス紹介もあわせて動画に組み込み、アニメーション動画の手法でサービス紹の利用方法を分かりやすく表現しました。
以上、CINEMATOが過去に制作してきたHow To動画の一例をご紹介しました。
How To動画のイメージは掴めてきたでしょうか。
では、続いては、How To動画の活用シーンを確認し、よりHow To動画の解像度を上げていきましょう。実際の動画があるとより理解が深まりやすいので、動画事例とともにご紹介していきます。
【事例付き】How To動画(ハウツー動画)
の活用シーン

そもそもHow To動画とは、「商品やサービスの利用方法」や「~のやり方」など、わかりにくいものをわかりやすくするための動画のことです。
How To動画といっても、その活用シーンはいくつか存在します。代表的なHow To動画は以下のようなものです。
の利用シーン
- 利用方法を説明するHow To動画
- アフターケア方法を説明するHow To動画
- サービス利用までの流れを説明するHow To動画
- レシピ動画
上記4つのHow To動画が利用される活用シーンを、動画事例と併せて、詳しく解説します。
利用方法を説明するHow To動画
利用方法を伝えるためのHow To動画は、以下のような特徴を持つ商品やサービスにとって非常に効果的です。
・使い方によって使用後の効果が変わってしまう恐れがある商品
例 : 美容商品、医薬品
・利用方法が複雑でわかりづらい
例 : webサービス
下記にて、商品やwebサービスの利用方法を紹介したHow To動画の制作事例を、2つご紹介いたします。
美容商品のハウツー動画制作事例 : プリオール(PRIOR)
こちらは、美容ジェルの使い方を説明するHow To動画の制作事例。
手に取る美容液の適量や肌への正しい馴染ませ方を実演しながら説明しており、文字だけではわからない情報が分かりやすく伝わってきます。
文字の場合、人によって解釈が違うため、どれくらいの量なのか、どのように塗るのか、どんな効果があるのかというのは、実際に目で見ないと伝わりにくいものです。
How To動画を利用すれば、イメージではなく具体的にどのような効果があるのか、どんな使い方をすればよいのか目に見えるため、間違った使い方をする可能性は少なくなります。
また、How To動画は単純に購入してくれたユーザーにとって便利なだけでなく、商品購入を検討しているが「ほんとに効果があるのかな?」「使い方が難しくないかな?」と迷っているユーザーの背中を押すという効果も狙えるのです。
webサービスのハウツー動画制作事例 : Service Cloud
こちらはセールスフォースの営業支援システム「service cloud」のサービスについて説明するためのHow To動画制作事例です。
使いこなせば非常に便利なツールですが、できることが多い分操作は複雑で、何ができるのかというのが伝わらないというのが課題でした。
例えば、会社に導入が決定し、利用者に使用方法を説明するとします。その際、口頭で説明すると時間がかかり、人的リソースを割くことになります。
How To動画はこうした懸念点を一気に払拭することが可能です。
映像により細かな使い方を容易に説明できるほか、繰り返し利用できるため、人的リソースを削減できます。
アフターケア方法を説明するHow To動画
「購入後のアフターケア方法を説明する」動画の場合、購買行動の促進も期待できます。
特に、お掃除家電系の商品は、アフターケアが重要になるため、How To動画を利用するケースが増えています。
ケアが難しそうと購入をためらっているユーザーもいらっしゃいますので、商品の洗い方や、普段の手入れの仕方などが簡単だと知ると安心して購入できそうですよね。
また、コストカット効果があることも、How To動画導入により見込める期待のうちの一つです。店頭で実演する場合は人件費がかかりますが、How To動画ならどこのお店にも共通の動画を流すだけ。
実際にアフターケア方法を説明した動画の実例を見てみましょう。
ハウツー動画制作事例 : ロボット掃除機RULO
こちらは、panasonicのロボット掃除機RULOのアフターケアに関するHow To動画の制作事例です。
清掃が大変といわれるロボット掃除機ですが、この動画では「簡単に清掃できる」ということを説明しています。
店頭では紹介が難しいロボット掃除機の洗い方説明を、How To動画化することで解決したことに加え、動画を繰り返し利用することでコストカットにもつなげているのです。
サービス利用までの流れを説明するHow To動画
新規顧客の獲得を考える場合、ユーザーにとっては「新しく使い方を覚える必要がある」ということが購入障壁となります。
How To動画を導入すれば、利用までの動きを時間軸に沿って説明することができるため、「覚える」という障壁が取り除きやすくなるのです。
このように、サービスを利用するまでの流れを説明する場合にもHow To動画の利用がおすすめです。
ハウツー動画制作事例 : タイムズカーシェア
スマホを用いた簡単予約から運転開始に至るまで、サービス利用の流れが分かりやすく説明されているHow To動画の制作事例です。
今までに無いタイプのサービスの場合、「利用方法がわからないから」「メリットが伝わってないから」というような理由で使われないケースが多々あります。
実際に利用することを決めたけど、使い方がわからないというユーザーのためだけの動画ではありません。
動画を見た潜在顧客にサービスを宣伝し、「想像以上に便利そうだな」「意外に簡単なんだな」と感じてもらうことで購入障壁を下げる効果もあるのです。
また、利用までの流れに限らず、サービス実績やサポート内容、会員特典の説明も動画に含まれているため、サービスの利用検討者の購入を促進する効果もあります。
レシピ動画
How To動画は、料理レシピ動画とも相性が良いものです。
How To動画を利用すれば、一連の動作を映像として見ることができますし、手を動かしながらでも視聴可能です。
企業が導入するメリットとしては、レシピの中で使われる食材をアピールしすることができます。
ハウツー動画制作事例 : ジャワカレー
こちらの動画は、料理研究家のリュウジさんが考案されたバナナカレーの作り方のHow To動画の制作事例です。
動画制作主であるハウス食品が提供する商品は、動画内でジャワカレーのみ。
直接的にジャワカレーを紹介しているわけではありませんが、簡単・爆速レシピを紹介することで、間接的に「カレーを食べたい、同じものを作ってみたい」と思わせる効果があります。
その中でジャワカレーをレシピに加えることで、この味はジャワカレーを利用すれば再現できるのだと興味を示して購入して頂ける可能性が高まるのです。
以上が代表的なHow To動画の利用シーンです。How To動画の利用イメージは湧いてきたでしょうか。では、続いて、How To動画を導入した場合、企業様にどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。
How To(ハウツー動画)導入による4つのメリット・効果を紹介
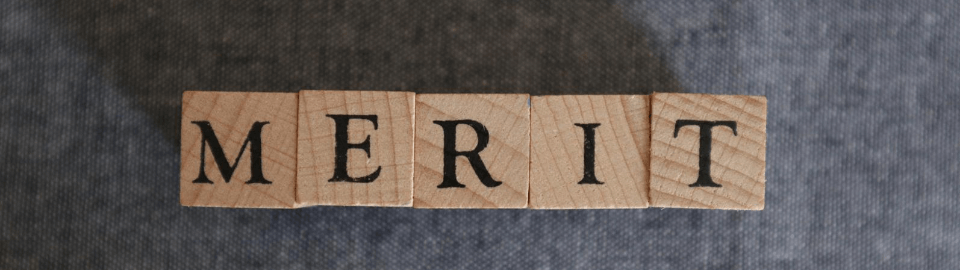
How To動画というと、ユーザー目線で見た場合「単純に使用方法を説明するための動画」と認識されることが多いですが、企業目線で見た場合、様々な導入メリットがあります。
導入のメリットは?
- 商品・サービスが持つ本来の魅力を伝えられる
- 使い方がわからないことによるお問い合わせを減らせる
- CX改善できる
- プラスαの魅力を伝えることができる
- 動画SEOを狙える
こちらでは、上記のHow To動画を導入するメリットを確認していきましょう。
商品・サービスが持つ本来の魅力を伝えられる
商品やサービスが持つ本来の効果を実感してもらうためには、ユーザーに正しい使い方を知ってもらうことが重要です。
WEBサービスでよくあるのが、色んな機能がありすぎて、何ができるサービスなのか伝わっていないこと。
魅力的な機能を備えていても、存在を知られていないかったり、有効的な使い方が伝わっていなければ、機能が無いのと同じになってしまうこともありえます。
このような場合に、How To動画の導入がおすすめです。
How To動画なら映像を通して使い方を詳細に伝えることができるため、知られていなかったサービスが持つ本来の魅力を伝えることができるのです。
使い方がわからないことによるお問い合わせを減らせる
商品やサービスの利用方法が少し難しい場合、カスタマーサポートに「使い方を教えて欲しい」といった問い合わせが多く寄せられている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときもHow To動画はおすすめです。
使い方が難しいと思われる箇所を予めHow To動画内で表現することによって、使い方に関する問い合わせを減らせる効果があります。
もしこのようなお問い合わせにカスタマーサポートの人員を増やしているのであれば、人件費削減にもつながります。
CX改善できる
※CX(カスタマーエクスペリエンス)…、購入前の検討段階から購入後のサポートまでを通した、購買プロセスにおける顧客が感じる体験。
How To動画を導入することによる大きなメリットの一つが、CXの改善です。
購入前、ユーザーは購入後のギャップをなくすために数々の情報を収集します。
How To動画を視聴いただくことで、実際にサービスを利用したらどんな体験ができるのか、映像を通じて安心感と納得感を持ってサービスの利用イメージを持って頂くことができるのです。
購入後、万が一使い方が分からなくともスマートフォン一つあれば確認でき、How To動画で簡単に利用方法がわかります。
また、説明書をいちいち紙面で管理する必要がないことも好評な要因の一つです。
プラスαの魅力を伝えることができる
このメリットは、特に料理レシピのHow To動画などで顕著に現れます。
レシピ動画の中で、食材の意外な組み合わせやメジャーではないレシピを紹介・説明することで、知られざる商品の魅力を伝えられます。
先程のバナナカレーが良い例でしょう。How To動画を見ることで、ユーザーはバナナとカレーのという意外な組み合わせに興味を持ち、カレーという商品の新たな魅力に気づくことができるのです。
レシピのHow To動画に限らず、ユーザーが「試してみたい」と思うきっかけづくりは、How To動画ならではのメリットです。
動画SEOを狙える
実は、動画はSEOにも効果的だと知っていましたか?
現在、Googleの検索結果には、Youtube動画が表示されるようになっています。また、検索結果上部には動画検索タブが用意されている検索キーワードもあり、そこには動画コンテンツのみが表示されます。
つまり、How To動画を制作すると、画像やテキストのみのコンテンツの時と比較して、単純にユーザーとの接触回数を増やすことができます。
また、今の時点では動画を掲載した記事は比較的少ないため、動画を掲載しているだけで優位に立てると言えます。
検索結果への表示方法は比較的簡単です。動画を記事コンテンツに貼り付けて、構造化データというコードを記事内に記述するだけ。
構造化データを使用しなくても表示されることはありますが、使用したほうがより表示の可能性は高まります。
How To動画は、会社紹介動画などの動画と比較して消費者が検索する可能性が高いため、動画検索などで上位表示できれば一定のアクセス数増加を狙えます。
こちらも、併せてHow To動画制作がおすすめな理由の一つです。
制作のメリットまとめ
- 本来の魅力を伝えられる
- 使い方がわからないという問い合わせ数減少
- CX改善
- プラスαの魅力を届けられる
- 動画SEOを狙える
続いて、How To動画のメリットを最大限に活かすにはどのようにHow To動画を制作すればよいのか、作り方のコツを見ていきましょう。
How To動画の作り方のコツ
ここでは、より効果が見込めるHow To動画の制作方法をご紹介します。How To動画の作り方で特に重要なポイントはぜんぶで3つです。
の作り方のコツは?
- 動画の尺は、短く・小分けにする
- スマホでの視聴を想定した画角にする
- 伝えたい情報を分かりやすく明確にする
1つずつ確認していきましょう。
動画の尺は、短く・小分けにする
How To動画の尺はなるべく短く・簡潔に、ニーズ毎に小分けにすることがポイントです。
一つの商品やサービスごとに詳細なHow To動画を制作しようとすると、尺の長い動画を作ってしまうことがあります。
しかし、ユーザーにかかる負担を考慮すると、15分の完全版How To動画よりも、ニーズ別に短く小分けにしたHow To動画の方が親切です。
なぜなら、ユーザーが知りたいことはHow To動画の中でも一部である場合が多いため。尺の長い動画だと、知りたい情報が説明されるまで待機する必要があり、負担になります。
またタイトルで動画の内容がわかるようすることで、ユーザーが知りたいこと内容なのか容易に確認できるようにしましょう。
スマホでの視聴を想定した画角にする
How To動画はスマートフォンで視聴されるケースが多いため、パソコンのみならず、スマートフォンで再生されることを想定した画角で制作しましょう。
動画編集ではパソコンを使用することが大半ですが、パソコン視聴のみを想定して制作することは禁物です。
スマートフォンで再生する際に、画角から飛び出した映像が表示されてしまわないよう注意しましょう。
伝えたい情報を分かりやすく明確にする
How To動画を制作する際は、内容を分かりやすく伝えるためにテロップをつけたり、実演を交えたりすることで、ユーザーに伝えたいことを明確にしましょう。
ユーザーが求めているのは「使い方を知ること」です。そのため、How To動画では派手な演出等は望まれていないことが多いです。
また、YouTube等でHow To動画を配信する場合、動画から購入につながるケースもあります。
単に使い方だけを伝えるのではなく、使用前と使用後を比較したような利用メリットを伝えることで、検討層の購入促進にも起因します。こうした企業様側で大切にしたい裏の意図も明確にしておきましょう。
制作のコツまとめ
- 動画は短く・小分けにする
- スマホ視聴を想定した画角にする
- 伝えたいことを明確にする
以上、How To動画の作り方のコツをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
大切なことは、それぞれの商品やサービスにあった表現を用いてHow To動画を制作することです。
もし、How To動画の制作に関して不明点がある場合、動画制作会社に相談することをおすすめします。
動画制作・映像制作ならCINEMATOにご相談ください
How To動画の役割は取扱説明書の代用品に留まりません。
How To動画を制作し活用することで、サービスの利用イメージを湧かせられたり、メリットを伝えることもできる他、認知獲得や比較検討層への購入への後押しにも繋がります。
How To動画を導入し、ユーザーへメリットを提供しながら自社のサービスをアピールしていきましょう。
もし、How To動画の制作をご検討中であれば、ぜひお気軽にCINEMATOにご相談ください。
コンサル出身で動画制作経験の豊富なメンバーが、マーケティング視点を持って、企業様の商品・サービスに最適なHow To動画をご提案いたします。
ご覧いただき誠にありがとうございました。

新卒でデロイト・トーマツグループに入社。その後、株式会社プルークスを共同創業、取締役に就任。大手、メガベンチャー企業を中心に多数のwebマーケティング・プロデュースを手がける。
2017 youtube ads leaderboard下期受賞経験を持つ他、2018年アドテック関西へスピーカー登壇。