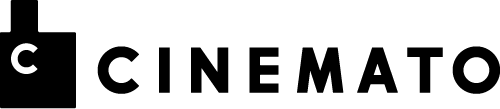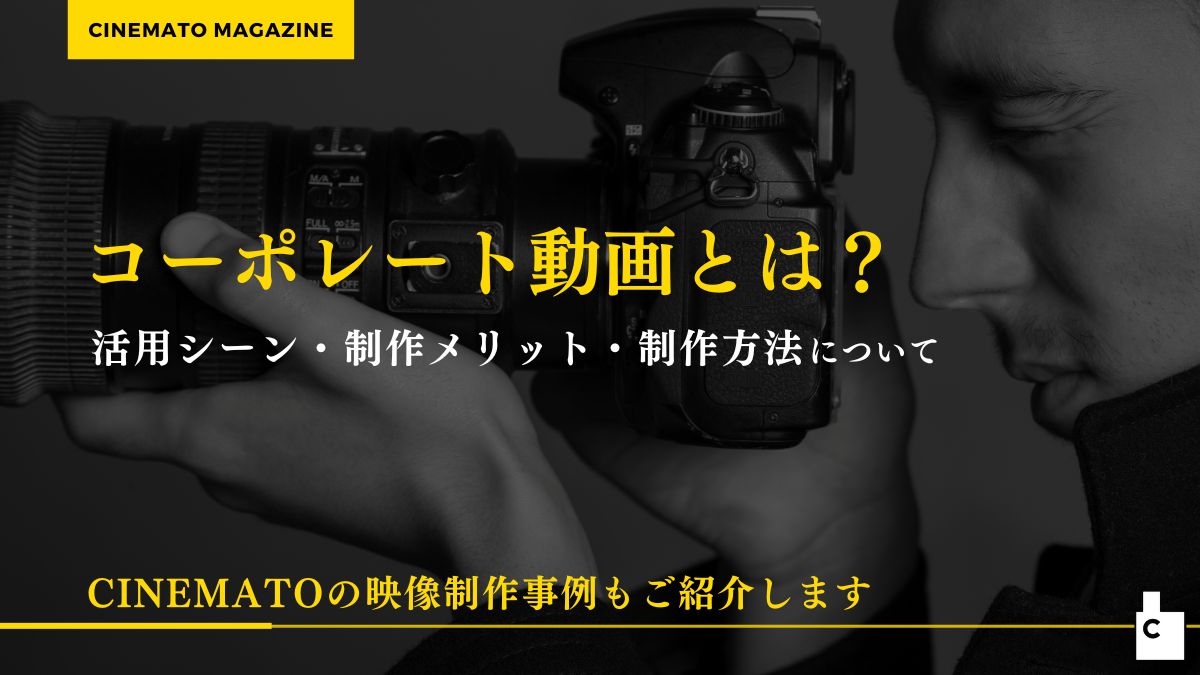スマートフォンの普及や通信技術の発達により急速に発展するデジタルマーケティング。中でもYoutubeやSNS広告で映像コンテンツが非常に身近になった今、多くの企業がコーポレート動画の制作に取り組んでいます。
コーポレート動画は、企業の魅力や事業内容を伝えるために制作される映像コンテンツです。
ただ、デジタルマーケティングに対する知見の少ない企業や担当者にとって「マーケティングに映像コンテンツを使用するメリットは?」「どういったシーンで活用できるのか?」と、不明点も多いことでしょう。
そこで、今回の記事では具体的に以下の疑問にお答えします。
- コーポレート動画にはどのような種類がある?
- コーポレート動画から得られる効果・メリットは?
- コーポレート動画はどのようなシーンで活用できる?
- コーポレート動画の実際の制作方法は?
それでは順番に見ていきましょう!
目次
コーポレート動画とは
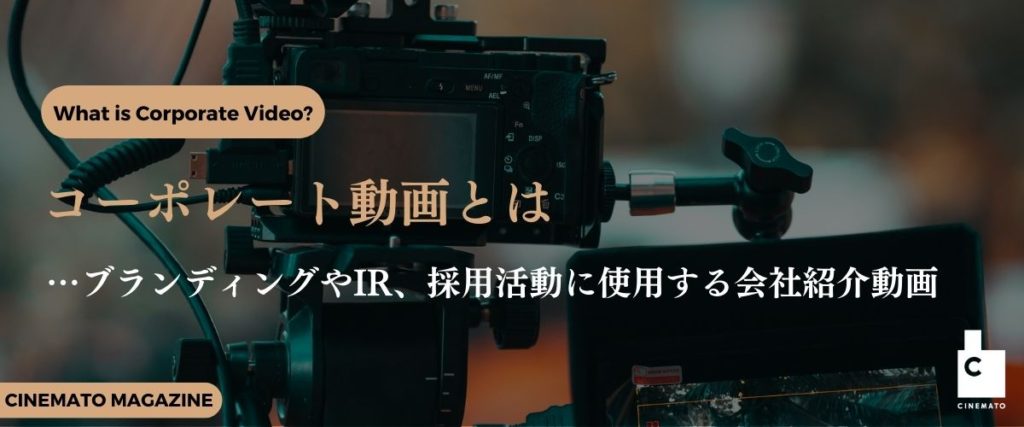
まず、コーポレート動画とは、会社を紹介する動画です。コーポレート動画には企業や事業の持つ「理念」や「ビジョン」、「価値」や「想い」といった抽象的な概念を表現することができ、ブランディングやIR、採用活動といった幅広い用途に使用されます。
動画は文字やテキストと比較して短時間で伝えられる情報量が多く、言葉では伝えきれない内容を情緒的に表現することが可能です。
これを活用することで、視聴者の心を動かし、企業に対する親近感・信頼感といったポジティブな感情を生むことができるでしょう。
コーポレート動画から得られる効果
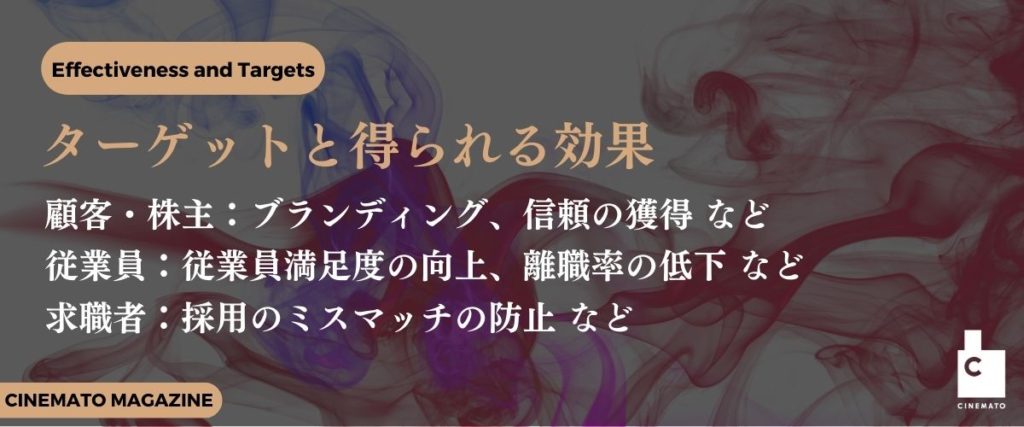
では、コーポレート動画を活用することで、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか?
ここではコーポレート動画の視聴者を「顧客・株主」「従業員」「求職者」に分類し、それぞれに与える影響を解説します。
- 【対顧客・株主】コーポレートブランディングに利用できる
- 【対従業員】従業員満足度の向上につながる
- 【対求職者】採用・求人活動に役立つ
【対顧客・株主】コーポレートブランディングに利用できる
短時間で多くの情報を伝達することのできるコーポレート動画には、顧客や株主に向けたブランディング向上の効果を期待できます。
企業や運営する事業のコンセプトや理念に加え、「想い」た「こだわり」といった言語化が難しい内容を伝えることで、顧客・株主からの信頼や共感を得ることができるでしょう。
【対従業員】従業員満足度の向上につながる
コーポレート動画は従業員にとっての企業価値を高める、インナーブランディングにも効果的です。
インナーブランディングを実施することで、社員は仕事にやりがいを感じ、企業・社会への貢献意欲を浸透させることができます。その結果従業員満足度は向上し、生産性の向上や離職率の低下へと繋がります。
【対求職者】採用・求人活動に役立つ
新卒採用・中途採用に関わらず、コーポレート動画は採用活動の場面でも効果を発揮します。
求職者にとって、自身と企業の共通点があることは、就職先を決める上で重要な要素です。企業・事業・人の魅力をうまく伝え、求職者の「この会社で働いてみたい」という意欲を掻き立てましょう。
また、採用の場面においてコーポレート動画は採用のミスマッチを防ぐという効果も期待できます。そのため、ありのままの企業の姿を紹介することも重要です。
様々な活用シーン
このように、多方面に向けて会社をPRするコーポレート動画は、具体的にどのような場面で活用されるのでしょうか?この章ではコーポレート動画を実際に活用するシーンを紹介します。
- コーポレートサイト・オウンドメディア
- 求職者向けの企業説明会や採用サイトに
- BtoBの営業ツールとして
- 展示会・セミナーイベントの営業ツール
- WEB広告・Youtube
- 社員総会や株主総会などのイベント
コーポレート動画はオンライン・オフラインの様々な場面で利用できる映像コンテンツです。様々なシーンで効率的に動画を活用することで、コーポレートブランディングを高めましょう。
コーポレートサイト・オウンドメディア
企業のコーポレートサイトや自社で運営するオウンドメディアは、コーポレート動画によるブランディング向上を狙う上で重要です。
ここで配信するコーポレート動画は、すでに企業や製品に興味を持って訪れたユーザーに向けて配信する「企業の顔」のような存在です。商品情報だけでなく会社の魅力をふんだんに詰め込み、企業の価値を伝える映像に仕上げましょう。
求職者向けの企業説明会や採用サイトに
企業説明会や採用サイトは、求職者に向けて会社の魅力をアピールする場として、コーポレート動画の活用が有効です。
求職者向けのコーポレート動画は企業・事業を紹介する内容のものに加え、社長・社員のインタビュー動画など様々なバリエーションで作成できます。
採用の場面における動画の活用には「優秀な人材を獲得する」とともに、「採用のミスマッチを予防する」という目的があります。
求める人材像を明確にし、企業の成長に必要な人材獲得を実現しましょう。
BtoBの営業ツールとして
コーポレート動画は営業ツールとしても利用可能です。
特にBtoBの取引先企業は、自社の商品だけでなく企業文化や価値に注目することも多いでしょう。動画を用いて自社の事業に対する共感を得ることで、信頼や安心といった心理的な繋がりを構築することも可能です。
良好なパートナーシップを築くために、商品より先に自社の魅力を売り込みましょう。
展示会・セミナーイベントの営業ツール
展示会やセミナーでも映像コンテンツは活用できます。
特にこれらのイベントでは、自社を認知しない来場者に向けても動画を配信するため、コーポレート動画は有効です。
まずは企業や事業に対する理解を深めてもらうことで、「来場者」に「見込み顧客」となってもらい、その後の商談や資料請求へと繋げます。
多くの企業が参加するイベントで使用する動画の制作では、「少し見てみよう」と思わせる、来場者の足を止めるための仕掛けを意識しましょう。
WEB広告・Youtube
インターネットで動画を配信することが一般的となった今、Web広告やYoutubeでの配信を目的にコーポレート動画の制作をおこなう企業は増えています。
ネット上での動画配信は、SNSでの拡散効果が期待でき、オフラインでの映像公開と比べ、多くの人の目に触れる可能性があるのが特徴です。共感や驚きといったバズり要素を意識し、人に共有したくなるコンテンツ作成を目指しましょう。
社員総会や株主総会などのイベント
社員総会や株主総会はインナーブランディングを強化する上で重要な、動画の活用場面です。
業績報告や戦略発表を軸にしたIR動画、従業員のモチベーションを上げるイメージムービー、新入社員向けに社長インタビュー動画など様々な動画の種類を利用できます。
伝えたい内容が多い場合はセクションごとに動画を区切るなど、最後まで視聴者を飽きさせないための工夫が必要です。
会社の紹介に映像を活用するメリット
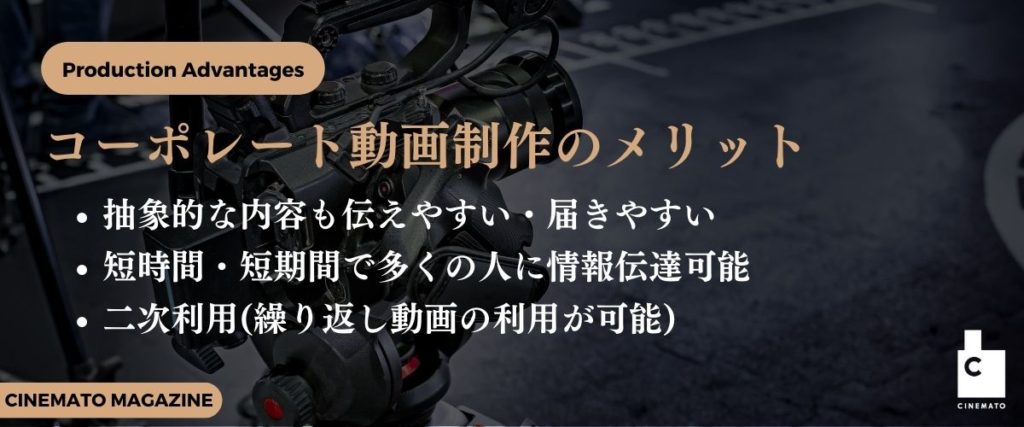
コーポレート動画の具体的な利用シーンがわかったところで、会社紹介に映像コンテンツを活用するメリットを見ていきましょう。
動画にはテキストや静止画と比べ情報伝達力に優れるなど、多くのメリットがあります。これらをよく理解し、自社での動画活用を前向きに検討しましょう。
- 抽象的な内容やイメージを伝えることができる
- 動画は短時間で多くの情報を伝達することができる
- 多くの人にコーポレートイメージを知ってもらえる
- 動画は静止画よりユーザーの心に届きやすい
- 一度制作すれば多くの場面で繰り返し活用できる
抽象的な内容やイメージを伝えることができる
会社の紹介に動画を活用するメリットの1つ目に、映像は抽象的な内容やイメージの伝達に優れているという点が挙げられます。
例えば情緒的なものを表現するには実写を、概念的なものを伝えるにはアニメーションを選択すると良いでしょう。動画はその目的に応じて様々な表現が可能です。
動画は短時間で多くの情報を伝達することができる
動画は記事コンテンツや写真と比べ、短い時間で多くのことを伝えることが可能です。ある調べによると、1分間の動画で伝えられる情報量は、文字に換算して180万語に匹敵すると言われています。
「明るく楽しい社内の雰囲気」を表現しようとした際、動画とテキストどちらを使用すれば早く正確に情報を伝えられるかは、言うまでもないでしょう。
多くの人にコーポレートイメージを知ってもらえる
動画コンテンツは、大勢に向けて情報を届ける際にも有効です。
というのも動画コンテンツは、インターネットを利用することで、時間や場所といった物理的な制約を受けずに情報を届けることができます。
「いつでも」「どこでも」視聴できる動画コンテンツの活用は、行動制限を余儀なくされるコロナ禍では、特に有効です。
動画は静止画よりユーザーの心に届きやすい
1971年にアメリカの心理学者によって提唱された「メラビアンの法則」によると、人が受け取る印象は、言語情報・視覚情報・音声情報によって形作られるとされています。
これら3つによって構成される動画は、文字のみ、音のみの時と比較して、視聴者の受ける印象に強く作用することのできる情報伝達手段です。
一度制作すれば多くの場面で繰り返し活用できる
動画コンテンツは制作にある程度まとまった費用がかかるものの、一度制作すれば多くの場面で繰り返し利用可能です。
例えば、同じ動画を何度も採用イベントで利用するといったことはもちろん、採用ムービーをWeb広告に転用するといったことも可能です。
1本の動画の視聴回数(再生回数)を増やすことで、動画制作の費用対効果を高めましょう。
コーポレートムービー3つの型とCINEMATOの動画制作事例
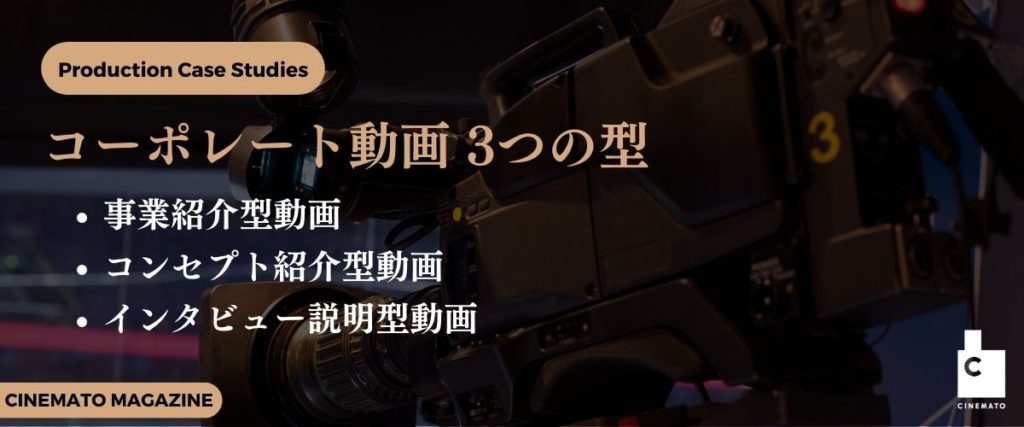
このように、様々な活用シーンや多くのメリットを持つコーポレート動画ですが、基本的には大きく分けて3つの型に分類することができます。
- 事業紹介型動画
- コンセプト紹介型(ブランドメッセージ型)動画
- インタビュー説明型動画
本章ではこれらコーポレート動画3つの型について解説するとともに、CINEMATOが実際に制作した動画を紹介します。
いずれも動画の持つメリットを存分に活かした弊社の自信作となっておりますので、ぜひゆっくりとご覧ください。
事業紹介型動画
事業紹介動画とは、企業がおこなう事業に焦点を当てて紹介する動画です。事業紹介動画に組み込む内容には、主に以下のようなものがあります。
- 企業概要・会社の歴史
- 業界の説明
- 提供する商品・サービス
- 代表メッセージ
- 従業員インタビュー
採用の場面では求職者の入社志望度アップ、営業の場面では取引先からの信頼感アップを目的に、動画を公開します。
IRの場面では新規に取り組む事業を紹介することで、株主の期待感を膨らませる効果を得られるでしょう。
一般的に動画の尺は5〜10分程度で制作することが多く、その中で会社や取り組む事業について、網羅的に説明します。
コンセプトや想いといった概念的なものを説明する際にはアニメーションを使用し、会社理解を促すのがおすすめです。
CINEMATO映像制作事例:株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー様
株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーは、様々な素材の組み合わせによって付加価値を持った製品を提供する複合素材メーカーです。
本動画では現在の自動車メーカーを取り巻く環境から課題提起。課題に対し自社の製品をどのように活用するかを提案するとともに、製品のメリットを解説しています。
動画のポイントは「樹脂」や「フィルム」といった専門的かつ目に見えない素材や機能に関する内容をアニメーションを使用して説明している点です。
その分野に知見のない顧客や一般消費者にも理解できるという意味で、動画の持つメリットが存分に生かされた事例と言えるでしょう。
CINEMATO映像制作事例:バリュエンステクノロジーズ株式会社様
バリュエンステクノロジーズ株式会社様は、AI(人工知能)の開発だけでなく、DX戦略の策定やビジネスの設計から、データベースの再構築を含むシステム開発やAI導入までをワンストップで提供する会社です。
AIを用いたシステム開発などを行っていましたが、他社と何が違うのかを明確に打ち出すことができなかったことが課題であったことから、他社との違いをわかりやすく説明するための動画を制作しました。
提供しているサービスで「何ができるか」を、動画で一貫性を持たせて表現しました。また、映像のデザインは、コンサルティングというサービス柄、知的な印象を与えるスタイリッシュな映像を意識しました。
その他、事業紹介型動画、サービス・商品紹介型動画の制作実績については、以下のページをご確認ください。
コンセプト紹介型(ブランドメッセージ型)動画
コンセプト紹介型コーポレート動画は、具体的な事業内容より会社のコンセプトや理念に焦点を当てて制作される動画です。
ストーリー仕立てのドラマチックなシナリオを用い、主に会社のイメージを訴求します。制作の際は事前にコンセプトを明確にし、動画制作会社と認識のズレを作らないことを意識しましょう。
コンセプトがズレると「結果的に何が言いたいのかわからない動画」が出来上がる恐れがあるため、注意が必要です。
CINEMATO映像制作事例:トランスコスモス株式会社様
トランスコスモス株式会社の制作したコーポレート動画は企業の理念や事業内容をドラマチックに描いた採用ムービーとなっています。
建築・土木業界のデジタルフォーメーションを推進し、顧客の業務効率化や競争力強化に貢献するのが同社の業務。動画は実写に3D CGをを組み合わせ、アナログとデジタルを融合させる事業内容を想起させます。
企業の思いに賛同する志の高い従業員の獲得を目指し、建築業界における自社の使命を明言する点が非常に印象的です。
CINEMATO映像制作事例:株式会社出前館様
株式会社出前館は、全国の出前&デリバリー店にすぐ注文できる、デリバリー総合サイト「出前館」を運営するテクノロジー企業です。
株式会社出前館のコーポレーションビジョン「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の思想が視聴ユーザーにしっかりと伝わるよう、想いを動画で表現することに重きを置いたアニメーション・ナレーションを意識しています。「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」として、フードデリバリーの「あたりまえ」を創ってきた企業、そしてこれからも新しいライフインフラを創っていく企業としての挑戦の姿勢を、”事業に懸ける想い”をベースにナレーションとイラストで伝えています。
イラストは、シンプルなカラー・アニメーションにすることでコーポレートカラーを際立たせています。また、「届ける」「つなぐ」といったワードをイメージした線画アニメーションを使用しました。
その他、コンセプト紹介型動画の制作実績については、以下のページをご確認ください。
インタビュー型動画
インタビュー型コーポレート動画は、社員や代表のインタビューを軸に構成される動画です。主に採用の場面で、アウターブランディング(対外的なブランディング)を目的に活用します。
インタビュー型の動画は、社員や会社の雰囲気を伝えるのに有効です。会社の魅力や理念を社員が語るというシナリオで動画が進行するのが一般的と言えるでしょう。
CINEMATO映像制作事例:株式会社EXIDEA
株式会社EXIDEAが制作したコーポレートムービーは、社員のインタビューを中心に組み立てられた採用ムービーです。
同社は本メディアCINEMATOをはじめ、メディア運営を中心とした事業に取り組むWebマーケティング企業。
動画の中ではメディア運営という仕事に対する思いや、企業の文化が1人1人の社員の言葉で語られます。
インタビューを受ける社員の表情やそれを見守る社員たちの笑い声といった細かな情報から、真剣かつ楽しんで仕事に取り組む社内の空気感が伝わります。
CINEMATO映像制作事例:株式会社Game With様
株式会社Game With様は、ゲーム情報等の提供を行うメディア事業を運営している会社です。
採用活動において、ゲームメディアを運営している企業であるという認知はされていたものの、実態とは異なるイメージを持たれているケースも多いのが課題でした。そのため、会社のカルチャーや働いている人を紹介する動画を制作しました。
インサートカットを多く入れることで、企業のリアルを追求することを意識しました。インタビューの中でのインサートカット挿入は、話している内容をより具体化的にイメージしやすくなります。
その他、インタビュー紹介型動画の制作実績については、以下のページをご確認ください。
動画をつくる上で押さえておくべき5W1H
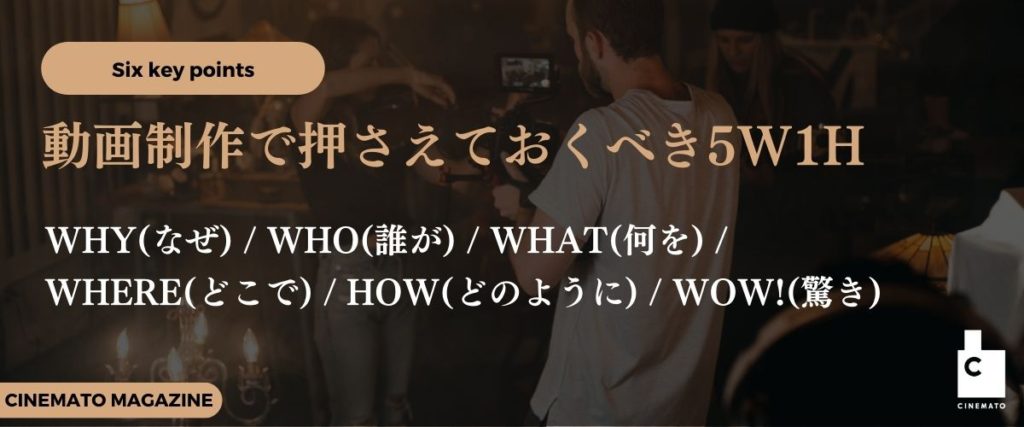
どのような型の動画を制作する際にも、必ず実施しなければならない作業があります。それは「5W1H」を明確にするということです。
- 「なぜ」動画を作るのか(WHY)
- 「誰が」ターゲットか(WHO)
- 「何を」伝えるのか(WHAT)
- 「どこで」使うのか(WHERE)
- 「どのように」伝えるか(HOW)
- 「驚きや気づき」を提供できるか(WOW!)
動画制作を社内・社外どちらでおこなう際にもこれらを設定し、制作意図とずれのない仕上がりの動画を作るための土台として利用しましょう。
「なぜ」動画を作るのか(WHY)
動画制作に取り組む際、まず初めに「なぜ」動画を制作するのかを明確にしましょう。
「認知拡大」「ブランディング」「信頼の獲得」。動画を用いて達成したい目的が何かを定めることで、内容にブレのない動画を制作するための軸が出来上がります。
達成したい目的が複数ある場合には、それらの優先順位を決め、制作会社との意識統一を図りましょう。
「誰が」ターゲットか(WHO)
動画の目的と同時に「誰に」訴求する動画なのかを設定することは欠かせません。
この時、あまりに広い範囲をターゲットすることには注意が必要です。ターゲットを広げることは一見良いことにも思われますが、裏を返すと「誰に向けた動画かわからない」印象のぼやけた仕上がりになりかねません。
企業のメッセージを伝えるためには、明確なターゲット設定が必要です。
「何を」伝えるのか(WHAT)
「WHY」「WHO」が明確になったら、次に「何を伝えるか」を検討します。
コーポレート動画では理念やコンセプトといった、企業らしさを表現することに重きを置きます。もし「らしさとは何か?」と言ったことが明確でないのであれば、動画制作をきっかけに社内の共通認識を作り上げるのも良いでしょう。
「どのように」伝えるか(HOW)
「WHY」「WHO」「WHAT」の設定を終えたらここではじめて「HOW(どのように伝えるか?)」について議論しましょう。
よくありがちなのは「HOW」から議論を始めてしまい、コンセプトが不明確になるという失敗です。
具体的には「モノクロのドラマ仕立てで・・」「ドローンで撮影して・・」など、何も決まらない段階で撮影や編集の話をしてしまい、結局何が言いたいのかわからない動画が出来上がるといった具合です。
逆に「WHY」「WHO」「WHAT」が定まっていれば、動画の軸はブレません。左記を定めたのちにテーマを伝えるために必要な「HOW」を考えるという順序を間違えないようにしましょう。
「どこで」使うのか(WHERE)
制作する動画の土台が出来上がったら、次にその動画を「どこで」公開するのかを検討しましょう。
動画コンテンツは様々な場面で活用することができますが、残念ながら全てのシーンで効果を発揮できる、万能な動画というものはありません。動画を公開するシーンや媒体によって様々な特性があります。
目的やターゲットに合わせた適切な「WHERE」を選択することで、動画マーケティングの効果を高めましょう。
「驚きや気づき」を提供できるか(WOW!)
ビジネスに活用する動画コンテンツにも「WOW」の要素は欠かせません。
というのも、どれほど素晴らしい内容を伝えていても、ロジカルなだけでは視聴者を動かすことはできません。頭でなく心、左脳でなく右脳に刺さる動画を制作することで、視聴者の心と体を動かしましょう。
知っておきたい動画制作のプロセス
以上のコーポレート動画を制作するメリットや効果といった内容で、動画制作の必要性については十分にご理解頂くことができたかと思います。
ここからは実際に動画制作会社を使ってコンテンツを制作する手順をお伝えします。
動画制作は大きく分けて4つのステップに沿って進行します。完成まで全体の流れを把握し、1つずつ作業を進めていきましょう。
- 動画の5W1Hの設定
- 動画制作の委託先を探す
- スケジュールと予算の設定
- 制作フロー(企画〜編集)の決定
動画の5W1Hの設定
前の章でもお伝えした通り、動画制作をおこなう際にはその土台を築いておく必要があります。そのために事前に社内で準備しておくべきことが5W1Hの設定です。
これらを明確にしておくことで、社内はもちろん制作会社の担当者との認識が揃い、イメージにブレのない制作作業をおこなえます。
少なくとも「WHY」「WHO」「WHAT」の3項目は社内で設定し、制作会社との相談のもと「HOW」「WHERE」「WOW」を考えましょう。
動画制作の委託先を探す
5W1Hの設定が済んだら、次に動画制作会社を探します。動画制作会社によって費用やオプションといった様々な違いがありますが、ここでは委託先を探す上での重要なポイントを紹介します。
- コーポレート動画の制作実績が豊富かどうか
- フィーリングが合い、一緒に仕事したいと思えるか
一言に動画制作会社といっても、各企業の得意分野は様々です。中でもコーポレート動画を含む、企業が制作する動画コンテンツには、マーケティングの知識が必要となります。
コーポレート動画の制作実績が豊富な会社に依頼することで、専門的なマーケティング知識を活用した動画を制作できるでしょう。
また、制作会社を選ぶ際、フィーリングが合うというのも実は重要です。
動画制作の現場では依頼者は雰囲気やイメージを言語化して担当者に伝えるケースが多々あります。この時フィーリングがあう担当者かそうでない担当者かによって、コミュニケーションコストに大きな差が出るでしょう。
「この担当者と仕事をしたい」と思えることは、案外重要です。
スケジュールと予算の設定
当然内容にもよりますが、企画から納品まではおおよそ3ヶ月程度をみておく必要があります。
予算は必要な人員や制作期間によって上下します。動画制作の費用は、30万円ほどで撮影できるインタビュー動画から、数千万円かかるコンセプト動画まで、幅があるのが特徴です。
制作を外部に委託する場合、予算と納期をあらかじめ伝えた上で提案をおこなってもらうと良いでしょう。
制作フロー(企画〜編集)の決定
動画の制作フローには大きく分けて3つのステップがあります。
- 企画
- 撮影(イラスト作成)
- 編集
企画
企画とは実際の制作作業に入る前に、動画の目的の設定やシナリオ作成、全体のディレクションを決定する作業です。
この段階でシナリオや撮影方法といった動画本編の内容、また演出やそれにかかる費用等が決まってきます。
後から動画の内容を大幅に変更することは困難です。制作担当者と十分なコミュニケーションをとり、不明点をなくした状態で撮影に進みましょう。
撮影(イラスト作成)
企画を終えたら、次に取り組むのは動画の素材作りです。実写動画の場合は撮影、アニメーション動画の場合はイラスト作成がこれに該当します。
撮影は制作会社の担当者とカメラマンをはじめとする技術者のみで進行することも可能ですが、できる限り立ち会うのがおすすめです。
ここでも気になる点があれば随時質問し、イメージを擦り合わせていきましょう。
編集
撮影やイラスト作成といった動画の素材作りを終えたら、最後に動画編集作業へと移ります。
編集作業は素材の繋ぎ合わせ、テロップやアニメーションの挿入、音響の調整の順で勧められ、これらの作業とチェックを終えたらコーポレート動画は完成です。
まとめ:コーポレートムービーは制作必須のマーケティングツール
本記事では現在多くの企業が注目する動画マーケティング施策の1つ、コーポレート動画について解説しました。
コーポレート動画は社員・株主・取引先といった企業のステークホルダーや、今後の入社を検討する求職者に向けても会社の魅力をアピールするマーケティングツールです。
制作時には改めて動画の5W1Hを明確にし、大きな成果を得られるコンテンツを作成しましょう。
\CINEMATOへのお問い合わせはこちら/

新卒でデロイト・トーマツグループに入社。その後、株式会社プルークスを共同創業、取締役に就任。大手、メガベンチャー企業を中心に多数のwebマーケティング・プロデュースを手がける。
2017 youtube ads leaderboard下期受賞経験を持つ他、2018年アドテック関西へスピーカー登壇。